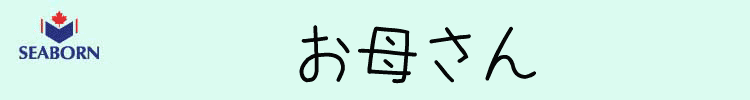第43回バンクーバー国際映画祭(VIFF)が北米プレミア上映となる「ぼくが生きてる、ふたつの世界(英題:Living in Two Worlds)」(日加トゥデイ・メディアパートナー作品)。原作は、作家・エッセイストの五十嵐大による自伝的エッセイ「ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと」で、本作では、コーダ(Children of Deaf Adults/きこえない、またはきこえにくい親を持つ聴者の子どもという意味)の主人公・五十嵐大(吉沢亮)の「きこえる世界」と「きこえない世界」での葛藤と成長の姿を描く。

現在、子育てと仕事の両立に多忙を極める呉美保(お・みぽ)監督は今回の映画祭への出席は見送ったが、バンクーバーでの上映に先立ち、東京から本作に込めた思いを語った。
—国内外で高い評価を得た「そこのみにて光輝く」以来、9年ぶりとなる長編監督作品となる本作。「映画にもう一度戻る勇気がなかった」という呉監督が、それでもこの作品を監督したいと思った理由は?
映画は四六時中そこに時間を割かなきゃいけない本当に大変な作業なので、2015年に子どもを産んで以来、育児中心の生活となり、長編作品を監督することは難しいと感じていました。しかし、2人目の子どもが1歳になった頃にこの企画をいただき、本作が息子と母親の話であり、私たちの生活の延長線上にある話で、なにより社会的マイノリティを描いている点に興味を引かれました。
原作を読むまでコーダのことは知りませんでしたが、そこに流れている感覚が自分の幼い頃の感覚に似ていたんです。私は在日韓国籍で、そのことでいじめられた経験はないですが、「あれ、私は他の人とはちょっと違うの?」、「『普通』って何だろう?」と思っていた当時の感覚を思い出し、この作品は、コーダの人だけではなくこの社会で生きるいろんな人たちに共感をしてもらえる物語、普遍的な物語にできるのではないかと思い、ぜひともこれを映画にしたいと思いました。
また、この企画をいただく2年前に私のめいが元々あった聴力を高熱で失い、ろう学校で手話の勉強を始めたんです。会うたびに、手話を習得して吸収していく様子にびっくりして、本当にすばらしいな、こういう世界もあるのだと気付かされたことも、この作品に引かれた大きな理由です。
—制作が始動すると、9年前にはなかった母親としての不安との闘いだったという監督。そんな状況の中、作品でこだわったことは?
今回、9年ぶりの長編監督作品としてのプレッシャーよりも、子育てと両立ができるのかという不安が大きかったです。「今日子どもが熱を出したらどうしよう」とか、「この打ち合せが子どもの迎えの前までに終わるのだろうか」ということを常に考えて、ずっと動悸がしている状態で1日中不安を抱えていました。
限られた時間の中でも特に作品でこだわったのは、「違和感をなくす」こと。この作品の原作は実話なので、作られたような世界の描き方にはしたくないと思っていました。例えば、この作品では、ろう者役は、全てろう者俳優に演じてもらっています。ろう者の方々に聞くと、今まで多くのろう者役を聴者の俳優が演じてきたけど、「外国人が生粋の日本人を演じているような違和感があった」と皆さんおっしゃる。よくよく考えると当たり前なのですが、実は気付いていなかったことに今回たくさん気付かされました。

また、この作品では観客がドキュメンタリーを見ているような感覚になるように、主人公・五十嵐大の0歳から28歳までを描くことが目標でした。映画「6歳のボクが大人になるまで」では何年もかけて実際に撮影されていますが、この作品の撮影期間はわずか3週間でしたので、幼少時代から吉沢亮さんまでの変遷を違和感なく見てもらえるように、とことんオーディションをやり、「ミニ吉沢亮」を探し続けました。
—撮影中、監督自身の感情が最も動いた瞬間は?
吉沢さんが父親と線路沿いを歩く長いワンカットのシーンの撮影だったのですが、吉沢さんの初めての手話のシーンですし、電車のタイミングやワンカットでの撮影など、難しい要素が多く、1回ではOKは出せないだろうと思っていました。

でも、びっくりしたのですが、ワンテイクで、吉沢さんの手話の間違いもなく、カメラワークもよく、電車もベストなタイミングで走り、うわーっと思いました。吉沢さん、持ってるなと。そのとき、「この映画は、きっとうまくいく!」と確信しました。今考えてもわくわくします。いまだに試写で見るたびに、もう完成しているのに、セリフの間違いないかなとドキドキして。そして毎回感動します(笑)
—本作では、ろう者と聴者間のコミュニケーションの問題が描かれています。手話を作品で扱う上で、苦労したことはありますか?
今回最も苦労したのは、「手話」という「異文化・異言語」を理解することのハードルで、ロスト・イン・トランスレーションといいますか、本当に忍耐勝負でした。話し言葉もたくさんの言い方が人それぞれあるように、手話の場合も、年代、性別、方言、性格によって全然違い、言葉の選択も違うため、まず、各キャラクターにのっとった手話翻訳をし、そのあと実際の俳優も交えて一緒に精査をして、現場でさらにもう一度修正するということを何段階も行って、手話を作り上げていきました。
現場にはおおよそ8人の手話チームが常駐し、ろう者俳優と話すときは、手話通訳に入ってもらい、手話演出メンバーともメールなどの活字での打合せが必要でしたので、やはりこうして話すよりも2倍、3倍の時間を要しました。そのときの疲労は想像以上で、英語が話せないのに海外に行ったときの疲れと同じ感覚でした。しかし、そこで少しでも気を抜くと自分の目指すところには行けないと思ったので、諦めずに最後までやり抜きました。
—バンクーバー国際映画祭で期待していることは?
私にとっての初めての国際受賞は2014年のモントリオール世界映画祭で、そのとき、カナダの人たちがとてもおおらかに迎え入れてくださったことを今でも覚えています。今回私が描いたコーダの主人公は、確固たる夢があるわけでもなく、何をしたいのかも分からない。主人公が「第一歩を踏み出すか、踏み出さないか」のような日本独特の空気の映画をカナダという多文化の国の人たちが、どのように受け止めてくれるのかすごく気になります。日本の片隅の、何でもない男の子の人生を見守るように楽しんでもらえたらなと思います。
「ぼくが生きてる、ふたつの世界(英題:Living in Two Worlds)」上映日時・会場
9月26日(木)8:30 pm @The Cinematheque
9月30日(月)10:30 am @International Village 9
https://viff.org/whats-on/viff24-living-in-two-worlds

(取材 佐々岡沙樹)
合わせて読みたい関連記事