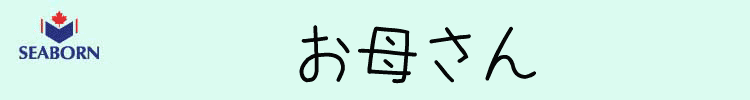第43回バンクーバー国際映画祭(VIFF)が10月6日に幕を閉じた。毎年VIFFでは日本映画が多く上映され、今年は長短編合わせて9作品がバンクーバーの観客に披露された。
カナダプレミアとなった作品も多く、9月29日と30日には「VIFF Short Forum」正式出品の「My Dog is Dead」がワールドプレミアとして上映された。
上映に合わせて、松永侑さんと千田丈博さんの両監督と主演の大石奈央さんが来加、上映後のQ&Aセッションにも参加した。10月1日にはバンクーバー市内で日加トゥデイのインタビューに応じ、映画制作への思いを語った。
愛犬を失った喪失感と共感のずれ

「My Dog is Dead」は9分間の短編映画。愛犬を亡くしたリコと、犬を飼ったことがない彼氏ヨシキの感情のずれを描いた物語。
映像ディレクターとして活躍する松永さんと、企業VPディレクターとして活動する千田さんの共同監督作品で、主人公リコを演じたのは俳優の大石さん、リコの恋人ヨシキ役にはSANOKAN PRODUCEを主宰する佐野寛大さんがキャスティングされている。
映画では、リコとヨシキの感情のすれ違いがパーキングエリアでの会話や車内の無言のシーンを通じて表現される。犬を亡くし喪失感を覚えるリコと、その悲しみを理解できないヨシキの距離感が、日常の中に潜む「共感の難しさ」を表しながらも、ユーモアを交えて描かれている。
上映後のQ&Aセッションでは、司会者や観客から映画のテーマについて質問が投げかけられた。

松永監督は「まず見て欲しいのが、犬の葬式なのに正装をしているリコと、その後ろにカジュアルな服装を着ている人たちで、主人公と家族のギャップを描こうと思いました」と語った。リコが犬の死を悲しむ様子と普段着でその場にいる家族やヨシキとの対比は、リコと周囲との感情の違いを象徴的に示している。
映画制作に至った経緯について千田監督は「僕たちは(同志社)大学の映画サークル出身で約8年前から映画を一緒に作ってきました。大学を卒業して社会人になった後、もう一度(映画を)作ろうという話になって勢い任せに作った映画なので、それがこのようにバンクーバーで上映されてうれしいです」と語る。制作当初は、国際映画祭での上映が実現するとは思っていなかったという。
観客からは、母親らと食卓を囲むシーンについても質問があった。唐揚げをうれしそうに頬張るヨシキの横で、リコが箸で唐揚げを机の下に忍ばせるシーンがある。この行動は子どもの頃に愛犬コッペに食べ物をあげていた記憶を思い起こさせるシーンだ。そこで、不思議なことが起きるのだが、「机の下に何かがあるのかもしれない」と想像してもらいたかったと話しながらも、実際の撮影時にはアシスタントディレクターが机の下で箸を折るという演出があったという裏話に会場からは笑いが起こった。
撮影には、千田監督の家から持ち込まれた食器や実際に飼われていた犬の小屋などが使われ、細かな演出には日常のリアルが詰め込まれているという。観客からも「日本の食卓の様子や畳などから日本らしさを感じた」という声があがった。
松永監督、千田監督、大石さんインタビュー
「Strange funnyな映画だ」
3人ともカナダを訪れるのは初めてという。バンクーバー国際映画祭への正式出品作品に選ばれたときの驚きを「バンクーバーで上映されるなんて信じられなかった」と笑いながら語った。
現地での評価について、関係者の間で「一つ変な映画がある」という声があがり、「次のシーンで起きるはずのないことが起きる“Strange funny”な映画だ」と注目されたという。
「私たちにとっては当たり前のことが、現地の観客には文化的に新鮮で興味深いものだったと気付かされました」と大石さん。監督も「日本では響かなかった部分に評価をいただけてうれしい」と笑顔を見せた。
自然と生まれた絶妙なギャップとすれ違い
この作品は松永・千田両監督それぞれの経験から生まれた。松永監督は新型コロナウイルス禍で祖父と愛犬を立て続けに亡くしたという。長らく会えないまま迎えた別れとその後の弔いへの葛藤がリコの物語に投影されている。「この気持ちをどう処理すればいいのだろう」というモヤモヤした感情が、映画制作の動機となった。
偶然にも千田監督のパートナーも同じ時期に犬を亡くしていたが、千田監督自身は犬を飼った経験がないという。犬の死を通じてお互いの感情に興味が生まれ、映画制作へと進むことになったと話した。
犬を飼ったことがない人は犬を亡くしたことへの悲しみは理解できるけれど、それがどれほどのものかは分からない。「共感しきれない感情や、人と人との関係性に興味が生まれて映画にしたいと思いました」と千田監督。
短期間かつ少人数での制作だったため、撮影当日が出演者の顔合わせだったという裏話も明かした。

大石さんは松永・千田両監督も所属した同志社大学の自主制作映画サークルF.B.I.出身。撮影当日まで一度も顔を合わせていなかったにも関わらず、「監督たちへの強い信頼があったから自然と演じることができました」と振り返る。現場での即興演技やアドリブのシーンが多かったものの、自然な初対面の空気が作品のリアルな雰囲気に生かされた。
また、リコとヨシキが話す言葉にもこだわりがある。リコと母親は関西弁を話すのに対し、ヨシキは標準語を使う。言葉の違いも二人の感情のズレを象徴的に見せる要素として描かれ、松永監督は「犬を飼ったことがある・ないというだけでなく、使っている言葉の違いなど小さな部分からも二人のギャップを表現できたのでは」と語る。
大石さんは実際には犬を飼った経験がなく、リコを演じる上でその感情の理解や表現に苦労したという。しかし、松永監督と同じ時期に新型コロナ禍で祖母を亡くし、脚本を手に取った時に作品のテーマに共感を抱いた。「やっていて楽しさがあった」と振り返る様子からは、撮影当日のわくわくした空気が想像される。同志社大学時代からの信頼関係が、日常に溶け込む独特の世界観を生んだのだろう。
巡り合わせと偶然が生んだ作品
他にもこだわりはあった。映画中の「音の変化」だ。
実は制作前から他の国際映画祭の短編作品出品に向けて制作することが頭の片隅にあり、海外の映画祭は音が非常に重要なため、短期間の制作の中でも音の使い方は意識したという。
「初めの雑踏のシーンで『ザワザワ』とした音から、映画の終わりにかけては徐々に静かになっていくんです」と話す。エンディングでは「映画が終わったというきっかけを預ける仕掛けがしたかった」という意図から、車が停車し、信号が変わるとともに発進するエンジン音で幕が閉じる。
エンディングではリコとヨシキにセリフはなく、どこか不調和な雰囲気があるこのエンディングからは、「この後にもしかしたら何かが起きるかもしれない」という期待感やリコとヨシキのすれ違いとチグハグ感が、観客の心に余韻を残す。
この作品の独特な世界観は、監督たちの実体験と偶然の出会いによって生まれた。予測できない展開とユーモアが交差しながらも、同時に心の奥にモヤモヤとした見えない感情を感じさせる。9分という短い中に詰め込まれたリアルな感情のズレと共感の難しさが、国境を超えカナダでも観客に強い印象を与えた。

(記事 田上 麻里亜/写真 斉藤光一)
合わせて読みたい関連記事