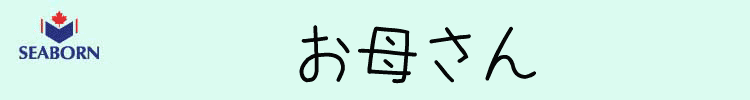小説家として活躍する西加奈子さん。2004年「あおい」でデビューし、以降次々と作品を発表している。2019年12月からはカナダ・バンクーバーに滞在。その時に乳がんが見つかり、バンクーバーで治療を受ける。その闘病記を自身初のノンフィクションとして発表した「くもをさがす」も話題を呼んだ。
2024年8月、バンクーバーに滞在していた西さんに話を聞いた。(後編)
「自分らしく生きるとは?」小説家・西加奈子さんインタビュー(前編)
作品について
多くの賞も受賞し、映画化された作品もあるほど人気のある西さんの小説。その原動力は「好きなものを書く」。書いた作品を読み返すと自分が感じていたことが「テーマ」として見えてくるという。
西さんは世代では「ロストジェネレーション世代」。自分ではコントロールできない社会情勢や日本の状況は「好きなものを書く」という小説に影響を与えているのだろうか?
***
-他のインタビュー記事で、「自分らしく生きる」「自分の人生は自分で決める」ということをテーマにしていると読んだのですが、「自分らしく生きられない」と感じているのでそういうテーマについて書こうと思うのですか?
「小説って不思議で、書いていたら自分が何を気にしていたかが分かるって感じなんです。なので、自分は海外で生まれたんですけど、ほぼ日本で育ったし、日本の価値観を完全に内面化して生きてきましたし、それに全く疑問を持った記憶はなかったんですけど、自分が小説を書くと、やっぱり自分はおかしいと思ってたんだなとか、ある程度の息苦しさを感じてたんだなというのを小説を書いてから気づくっていう感じです」
-小説を書く時に読者を想定して書かない、自分が書きたいものを書いているということですが、それは自分の書いたものが読者に届けばいいと思って書いている感じですか?
「とにかく書く時はまずほんとに自分が書きたいものを書く。それを世に出し得るかどうか、お金をいただいていいかどうかは編集者が決めると思っています。編集者がプロフェッショナルなので、彼らがボツと判断したらもちろん諦めます。ただ、最初に読者を想定して書くと下投げになってしまうというか、全力で投げることができなくなるのも嫌ですし、創作というのは元々すごくエゴイスティックなものと思っていて、特に小説は1人でするものなので『全力で自分の好きなものを書く』っていうのが一番失礼のないやり方かなと思っています」
-その中で自分のことは自分で決める、自分のなりたい自分になるというテーマは書いてるうちにテーマができてくる?
「ほんとに好きなものを書いてきて、結果、もちろんそうでないものもありますけど、自分の作品を見返した時に、社会から自分を取り戻すというか、社会的にこうでなければいけないとか、役割があったり、ある程度の窮屈さの中にいた人たちが、自分の身体性を持って自分を解放していくという話がすごく多くて。ということは、私はそう思ってたんだなとか、それが書きたいんだなっていうのを後から気づくって感じですね」

-西さんは自身をロストジェネレーション世代として意識したことはありますか?
「昔はそんなの思っていなかったんですけど、最近同世代の友達の中には、20代のうちはバイトで生活できていたけれど、年齢を重ねるにつれて仕事がなくて就職もできないという人がいます。いよいよほんとに捨てられていってるというか、再就職もかなわない、派遣社員っていうものができてからずっと派遣で正社員になれなくて、ダブルワークしているという人が本当にたくさんいるので、それは深刻に考えるようになりました。
あとはロストジェネレーションって特徴としてちょっと冷笑的なとこがある気がします。例えば、私もデビュー作を20代で書いたんですけど、結構、キラキラしたというか、ハッピーエンドな物語を書くと冷笑的に笑われてしまったりした経験があって、なんていうんですかね、良いことを書く、ハッピーなことを書くと恥ずかしいみたいなとか、それは私たちの世代の特徴なのかもしれないですね。
でも、例えばいまZ世代とか若い子たちとしゃべってるとみんなすごくハッピーだし、ハッピーな物語を求めてるし、すごくポジティブだし、もっと経済が悪くなってるのに、なんか冷笑的なものがなくなってきてるのはすごくすてきだなぁって思いますね」
-小説の中でロストジェネレーションをテーマにした作品はありますか?
「あります、あります。テーマというか、ロストジェネレーションの人たちが主人公で正社員になれなくて貧困にあえがざるを得ない話を書きました。
私は20代の時は就職しなかったんです。『就職せずによくいけたね』って言われるんですけど、ほんとにすごい就職氷河期だったので、フリーターが目立たなかったんですよね。同世代の作家もフリーターをやってた人はいますし、多分劣等感を感じずに済んだんです、当時は。生活もお金はなかったけど楽しかったし、友達に恵まれて、健康でしたし、それだけでハッピーでした。だた、だんだん年を取ってきて当時の友達とかに会うと、やっぱりさっき言ったようにダブルワークしていたり、親の介護が始まっているのにヘルプを出せなかったり、悲しいことに生活保護受給者に対してすごく辛辣な目を持っていたりとか。そういう話をしていくうちになんでだろうって思って書き始めたんです。
『夜が明ける』という作品なんですけど、それは『なんでそういうことになってしまったんだろう』とか、『自分だったらどうだっただろう』と自分自身に問う機会でもありました。私もたまたま作家で、たまたまある程度成功したからお金もあります。私は特権があったから今ここにいることができるけど、どうなっていたかは分からない。特権があるから、余裕があるから、例えば制度がおかしいと、『大きなこと』を考えられるけど、本当にいま自分の生活が苦しくて、ダブルワークで、親の面倒を見て、子どもの面倒を見て、ってなったらそんな『大きなこと』を考えられるかなって。
例えば、身近に生活保護を受けてる人がいたとして、『がんばってないからや』って言ってちょっと胸がすく、そういう夜を過ごしてなんとか生きていくようになるんじゃないか。ほんとにたまたま、全てたまたまなので。そういうことが、作品になっているんだと感じます」
-イラン生まれということですが、世界情勢で中東情勢は気になりますか?
「一番ガツンと来たのは、アラブの春の時です。エジプトが変わるんだって。ほんとにいま宗教のこと、そのことも小説に書いたんですけど、宗教という信じるものの違いによってこんなに人が傷つけあう状況ってなんなんだろうと考えます。それはもちろん中東だから特にってことではないですけど。
エジプトにいた時にすごく美しいムスリムの人たちを見ていてました。コーラン・アザーンが聞こえたらお祈りを唱える人たちが、私には排他的には見えなかったんです。ただ自分も、やはり特権があって良いエリアに住んでたし、優しい人たちに囲まれていたというだけで、例えば、当時もコプト教徒の人たちは迫害されていたし、そういうことを気づかなかった自分を思い出しながらまた書くという感じです」
-バンクーバーもそうですがカナダ全体で移民の国で、カナダの多様性をどのように感じましたか?
ほんとにカナダ人というものがなんなのか分からないくらいですよね。ビザとか書類の問題もありますけど、自分はカナダ人だと思ったらどんな見た目でもカナダ人でいれるっていうのはすばらしいと思いますし、先ほど言ったマイノリティの方が尊重される社会も素晴らしいと思います。
ただ、例えば私の子どもはキツラノのデイケア(保育園)とかキンダー(幼稚園)に行っていたんですけど、そこは見た目に関して非常に美しい多様性はあるんです。本当にさまざまな人種がいるし、先生ももちろん多様性があるし。ただ経済的には似通っているんです。皆それぞれ特権があってそこに住んでいる。目に見えづらい経済の問題が忘れがちになってしまうんです。
日本に帰っていま日本の公立に子どもを入れてるんですけど、見た目はほぼ一緒なんです、アジア人で、黒い髪で。でも、経済的には全然違う子どもたちが集まっているっていうのはそれも立派な多様性だと感じます。私はキツラノがほんとに好きだったけど、あまりにも分かりやすい多様性の中にいたのかなというのは思っていて、それを書きたいなと思っているところです」
-西さんにとって自分らしく生きるとは?
「自分らしさの特集とかありますけど、見つけるのは難しいと思うんですよね。自分らしさっていうと、イコールなんか何物にもとらわれてなくてみたいなイメージになりますけど、そうでなくてもいいと思うんです。
なにかにすごくとらわれてキュウキュウになってる自分も自分らしさだし。ただ、それが自分で選んだ自分だと良いと思うんですけど、社会に『Should beだ、君はこうあるべきだ』って言われて押し付けられたものだったら1回やめたらいいんじゃないかって思います。
自分らしさって言葉がまた呪いになるのもおかしいですし、ただなんか『自分が気にしちゃうんねん、もうすっごいあの人のこと気にしてどうで』って、それが私は自分らしくないっていうのではなくて、それも自分らしさだけど、なぜ気になるのかっていうのを掘って掘って掘っていく。それがほんとに自分がピュアに気になるんだったらいいと思うんです。それが『いや、あなたはその年でどうでこうでこういう立場やから、あの人のことを気にした方がいい』だったとしたら一回手放した方がいい。すごく大変な作業ですけど、それをひとつずつ重ねていっているっていう感じです」
-西さんは自分らしく生きてるなって思いますか?
そうですね。少なくとも、楽にはなってきてますね。なんかこうでないといけないとか、特に日本、世界中そうですけど、女性であって、中年女性であって、働いている女性であって、母であって、娘であってとか、役割が多いと思うんですけど、その役割にはこだわらないという風にはなりましたね」
***
バンクーバーについては「バンクーバーにはバンクーバーにしかない良いとこがあって、ほんとに自分が心地良い自分でいられる数少ない場所だと思います」と語った。
西加奈子(にし・かなこ)
小説家。イラン・テヘラン生まれ。小学生の時にはエジプト・カイロで過ごしたが、帰国後は大阪に。2004年「あおい」でデビュー。2007年「通天閣」で織田作之助賞、2013年「ふくわらい」で第一回河合隼雄物語賞、2015年「サラバ!」で第152回直木三十五賞を受賞した。映像化された作品には2013年に映画化された「きいろいゾウ」(2006年)、劇場アニメ映画化され、バンクーバー国際映画祭でも上映された「漁港の肉子ちゃん」(2011年)がある。「くもをさがす」は第75回読売文学賞 随筆・紀行賞を受賞した。
(取材 三島直美/写真 斉藤光一)
合わせて読みたい関連記事