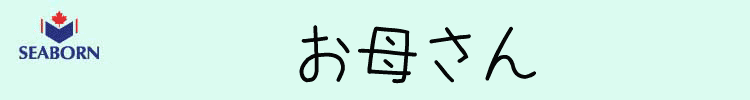エドサトウ
もし、仮に日本の古墳のアイデア(考え)が、前回に書いたように沖縄のお墓のような考えからきているとすれば、沖縄には古くから南方の文化があったように想像される。沖縄諸島の海底にある人工的に作ったとみられる建造物みたいな遺跡は、自然なもので遺跡ではないという説もあるが、まだ、沖縄諸島が台湾や大陸と陸続きの時代、縄文時代の初期の一万四千年ぐらい前には、祭事に利用されたのかもしれない。たとえば、奈良の三輪山とか、伊勢の夫婦岩のような自然信仰みたいなものがあったように想像もできる。日本の神話は南方起源としているものと似ている話が多くあると言うから、海底であるが、当時は陸地であるから、何らかの神事が行われた遺跡かもしれない。
鹿児島のずいぶんさきの種子島の海に鬼界島があって多くの縄文人が暮らしていたが火山の噴火により海中に消えてしまった。その後、南方の文化は宮崎県に落ち着き、そこで大きくなり、北九州に広がったとすれば、大阪の古墳のアイデアが沖縄あたりからきたことに納得がゆく。朝鮮にある古墳の天井が大きな岩ではなく、多くは材木で塞がれているのを見れば、あの大きな石で天井を塞いだ日本の古墳は台風などの大風を意識した建築物のように見えることは、大阪や奈良にジマ(島)大国の卑弥呼の源流である南日本のアイデアがあるようにも思える。だから、ジマ大国の卑弥呼は奈良に拠点を遷都したのではないかというのは、小生の夢想である。
沖縄では、1970年ころ、友の話ではシャーマン的な女性がいて、村を取り仕切っていたことは、女王卑弥呼につながるみたいで興味深い。
紀元200年ごろは、弥生時代からの寒冷期で気温が1度ぐらい平均的に低かったようである。気候の不順で作物の不作も考えられる。そのためか日本への渡来人が多かったのかジェノサイド(虐殺)もあったのではないかと言われている。283年、百済の王、裁衣工を貢上。この年弓月君百済より渡来する。284年、百済の王、阿直岐を遣わして良馬二匹を貢上する。また、289年、倭漢直の祖阿知使主が、その子都加使主および党類十七県を率いて来帰する。(おそらく300人ぐらいかと思います)」
かつて、多くの渡来人が出雲や福井の海岸から日本の内陸に進み定住したように想像すれば、「ーーー大和に置いてあおによし奈良山を越え、どのように思いになったのか、天離る都であるが、石走る淡海(渤海)の国の楽浪の大津の宮治めはここにあったと聞くけれどーーー」、ここにある「渤海の楽浪の大津の宮」と言うのは、北朝鮮にあった先進文化があったであろう中国の植民地の出先機関のような楽浪郡のことと言うのであれば、ひょっとしたら琵琶湖周辺には多くの渡来人が定住していたように想像もできる。ヤマトタケルが日本を統一しようとしたその帰り道に伊吹山で大けがをして、彼の同胞が住んでいたと思われる米原市の磯神社で治療を受けて滞在したことは納得がいく話である。
また、日本海の島根県の出雲から鉄を携えて大阪や大和の入ってくる朝鮮半島からの倭人も琵琶湖の周辺に定住して、半農半漁の自給自足の生活をしていたのではなかろうか?おもに、縄文人は岐阜県や愛知県の河川や海岸線に多く住んでいた。日本はまだ小さな縄文人集団が住んでいて、日本という大きな国の集団はできてなかったのを、新しい馬と鉄の文化を持ったヤマトタケルの軍団が日本という国のもとを創り上げたようにも想像もできる。全国にある神社、いわゆるお宮さんは、今でいうところの役所ではなかったのではと僕は思う。
神主さんは、指導者として水田と米作の指導や絹の生産を指導した文化人ではなかったのか?
冬になり、農作業がなくなれば、男達は大阪や奈良に向かい、泊まり込みで古墳などの建造にあたったのかもしれない。エジプトのピラミッドの建造のように、多くの人は奴隷ではなく、ご飯を食べ、お酒を飲み、楽しく力を合わせて大古墳の建造に携わっていたのだろうと僕は夢のような想像をする。多くの異なる地域の人々が交流して、「日本国家」の機運が高まってゆくのであろう。

投稿千景
視点を変えると見え方が変わる。エドサトウさん独特の視点で世界を切り取る連載コラム「投稿千景」。
これまでの当サイトでの「投稿千景」はこちらからご覧いただけます。
https://www.japancanadatoday.ca/category/column/post-ed-sato/